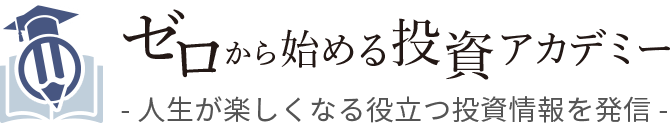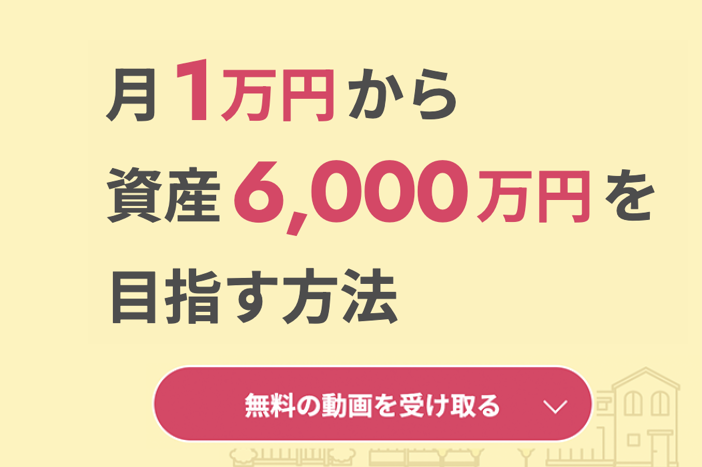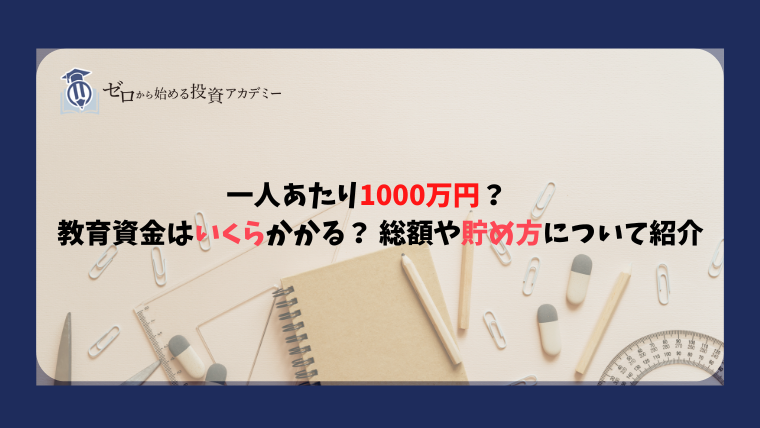
子供を持つ親御さんにとって、とりわけ頭が痛い問題は『教育資金』についてでしょう。幼稚園から大学卒業まで、一人あたりにかかる総額は1,000万円とも言われており、進路によってはさらにかかってしまう可能性もあります。
そこで今回は、子供の教育費はどのくらいかかるのか?
その総額や効率よく貯める方法、さらには貯蓄していく上で注意すべき点などについて紹介していきます。未就学児のお子様をお持ちの方はもちろん、これから中学、高校と進んでいくお子様をお持ちの親御さんにもぜひご一読いただけると幸いです。
≫ 簡単30秒 LINEで診断!「お金の健康診断」はこちら
≫ 無料講座:お金のプロが教える「毎月収入を得る投資の始め方」
 監修者:市川雄一郎
監修者:市川雄一郎
GFS校長。CFP®。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)。日本FP協会会員。日本FP学会会員。 グロービス経営大学院修了(MBA/経営学修士)。
日本のFPの先駆者として資産運用の啓蒙に従事。ソフトバンクグループが創設した私立サイバー大学で教鞭を執るほか、講演依頼、メディア出演も多数。著書に「投資で利益を出している人たちが大事にしている 45の教え」(日本経済新聞出版)
公式X アカウント 市川雄一郎@お金の学校 校長
子供の教育費はいくらかかるのか?
総額1,000万円とは言え、私立を選ぶか、はたまた公立を選ぶかによって大きく異なります。さらに、塾に通うなど習い事の費用も加わると、進路によっては総額1,000万円を超えてしまうこともあるでしょう。そこでまず、一般的にかかる教育資金の詳細や費用を軽減する方法について紹介していきます。
幼稚園から大学までにかかる総額は?
教育資金の総額は、一人あたり1,000万円と言われていますが、それはちょっと低く見積もっています。なぜなら、文部科学省が発表している「令和3年度子供の学習費調査の結果について」「国公私立大学の授業料等の推移」の数値を参考に、幼稚園から大学卒業までにかかる総額の平均を出すと、12,798,004円となるのです。
ただしあくまで平均であり、全て国公立を選んだ場合は平均より大きく下回る結果になりますし、逆に全て私立を選ぶと平均を大きく超える結果が出ます。進路ごとの費用については次項で詳しく説明しますが、進路はどうあれ、子供一人あたりにかかる教育資金の平均は1,000万円を超えることは間違いという点を認識しておくべきでしょう。
私立か公立かで大きく変わる
前項で少し紹介しましたが、通う学校が私立か公立かで教育費は大きく異なります。詳しくは下図の通りです。

文部科学省:「令和3年度子供の学習費調査の結果について」「国公私立大学の授業料等の推移」より集計
図の通り、幼稚園から大学卒業まで国公立を選んだ場合にかかる学習費の総額は6,280,564円であることに対し、私立の場合は19,315,445円にも上ります。その差は実に倍以上であり、かなりの高額になることがわかるでしょう。
思いがけず高額なのは公立の小学校の学費です。中学・高校が約150万円前後であることに対し、小学校では約200万円もの費用がかかっていることがわかります。年間に換算すると30万円強となり、この費用の中にはランドセルの費用や修学旅行などの学校外活動費も含まれ、さらに塾や習い事の費用も加味された金額になっています。
しかし、公立の小学校は原則として授業料は無償。つまり、それ以外にかかる平均総額が約200万円というわけです。
塾や習い事の費用も考慮すべき
習い事は様々ありますが、その代表格とも言える「塾」にフォーカスして分けると、小学生は公立の場合で120,499円、私立になると377,663円、公立に通う中学生は303,136円、私立で262,322円。さらに公立に通う高校生は171,377円、私立になると246,639円という結果が出ています。
ちなみにそれらの数値は、文部科学省が発表している「学習費調査」の数値を元にまとめたものになります。ただし、習い事は塾だけではありません。特に小学生の場合は塾以外にもスイミングや書道、そろばん、運動系スクールなど、様々あります。それらを加味すると、前項で紹介した小学生の学習費の平均が高いのも頷けますよね。
各種支援制度を利用して負担を軽減
教育資金が高額であることはこれまで紹介した内容を読んでもらえれば明らかです。それゆえに、一部ですが国から援助を受けることができます。今回は幼稚園から大学までにかかる教育費としているため、保育園は除く上に、公立の小学校・中学校は基本授業料が無償なので、該当するのは高校・大学になります。
高校の場合、受けられる補助は公立と私立で異なります。分けて解説すると・・・
公立高校の場合
「就学支援金」という助成制度で、公立全日制高校の年間授業料程度はほぼカバーできる額が支給されます。尚、支給額は家族構成などによって異なります。また、対象となる学校も全てではないため、文部科学省のサイトよりご確認下さい。
私立高校の場合
「就学支援金」と、「各自治体の助成金制度」を一緒に利用することで、授業料が実質無償となります。尚、「各自治体の助成金制度」は名称・金額ともに自治体ごとに大きく異なります。
例えば東京都の場合、世帯年収目安が約910万円以下の場合、47.5万円が補助金として支払われます。つまり、世帯年収が910万円を超えている世帯は実質学費が有償となるのです。
ちなみに、大学生の場合、助成金を受ける資格があるのは基本的に低所得世帯のみとなります。つまり、小学校から高校までは、収入によって授業料が無料になることに対し、大学の授業料は基本「有償」であると認識しておくべきでしょう。
さらに大学生の場合、負担を軽くする方法として挙げられるのが「給付型奨学金」です。これは、貸与型とは違い、返済する必要のない奨学金となるのですが、月の支給額は上限で5,000円、つまり年間60,000円もの額を得られることになります。ちなみに、貸与型の場合は結局返済しなければならない上に、余計な金利までかかってしまうため、負担を軽減するための策として有効ではないと言えるでしょう。
以下の記事では、よく混同されがちな「奨学金と教育ローン」を比較して解説しています。
教育資金を貯める方法として最適な手段は?
助成金を受けられたとしても、かかる費用の全てをカバーすることはできません。つまり、ある程度は自力で用意するしかないということです。とは言え、総額1,000万円以上、お子様の人数によってはその2倍、3倍もの資金を工面しなければならないとすると、簡単ではありません。そこで同章では、教育資金を貯める最適な手段について紹介していきます。
①預貯金
利息はあってないようなものなので、元金プラスαの期待はできませんが、1,000万円以下の資金を貯めるなら、預貯金を講じて教育資金を貯めるのも手です。ちなみに、銀行が破綻してしまった場合、補償される上限が1,000万円までというところがほとんどなので、それ以上預貯金する場合は、面倒ですが他行にも教育資金用の口座を作っておくことをおすすめします。
②学資保険
「学資保険」とは、子どもの教育費を準備するための貯蓄型保険のこと。保険料を支払い続けることで教育資金を貯めることができ、満期になると「満期保険金」や「お祝い金」として、契約で定めた金額を一時金または年金形式で受け取ることができます。
加入するメリットは、受け取るタイミングを選べる点や、払込途中で契約者が亡くなった際も、満額支払われる点。そして何より、契約形態によっては一時所得として所得税の対象となるものの、受け取った保険金と払った保険料の差額が50万円までは非課税になるという点もメリットと言えるでしょう。
③投資
株式、債券、投資信託と、投資の種類は様々ありますが、投資経験がない方や、投資に関する知識が浅い方におすすめなのが、投資信託です。
投資信託とは、運用の専門家である投資信託運用会社が、多くの投資家から資金を集めてファンドを作り、運用損益を投資家に還元するという商品。つまり、自身で運用する必要がないため、投資に関する知見が浅い方でも始めやすい商品なのです。
そして欠かせないのが、NISA制度を利用すること。NISAとは、長期的な資産形成に適した少額投資非課税制度のことであり、出た利益に対して税金がかかりません。税制優遇を受けながら、利益の全てを確実に得られるお得な制度である上に、加入基準はないので、誰でも利用できます。
教育資金を貯める際に注意すべきこと
これまで紹介した内容からもわかるように、進路を公立だけに特化したとしても、かかる費用は決して低くありません。それに、中・高が無償化になったとしても、それはあくまで授業料のみであり、教育資金の全てが無料になるわけではありません。
つまり、お子様がいる世帯は必ず準備する必要があるのです。そこで最後に紹介するのは、教育資金を貯める際、注意すべきことです。これから教育資金を貯め始める方はもちろん、現在進行形で貯金を進めている方も最後までお読み飛ばしなく。
児童手当には所得制限がある?
子育て世帯の一助として欠かせない児童手当は、子供が中学3年生まで支給されます。しかし受給するには所得制限があり、児童手当における所得制限が適用されるのは、収入額833万3,000円(所得額622万円)以上の場合とされていました。しかし、2024年10月からその所得制限が撤廃され、さらに第3子以降は3歳から受給額が3万円(これまでは1万5千円)にアップします。つまり、これまで所得制限を気にしていた方もいるかと思いますが、これからは所得に関係なく受給できることを覚えておくとよいでしょう。
教育資金用の口座は分けておく
これはもう言うまでも無いと思いますが、普段利用する生活費専用の口座と教育資金を貯蓄する用の口座は別にしておくべきです。貯金口座を普段使いできるようにしてしまうと、貯まるものも貯まりません。
お子様専用の貯蓄口座を作り、必要な時だけ使えるようにしておくべきでしょう。ちなみに預金口座は0歳から開設可能。児童手当を貯めておく口座として、生まれてからすぐ開設するのも良いと思います。
贈与税に注意
貯金とは少し離れますが、子供や孫へ教育資金を贈与する場合、年間110万円を超えた場合、その超過分に対して課税されます。
しかし近年、少子高齢化などの影響により、日本では個人金融資産の高齢者層保有率が高まっており、その背景から「教育資金贈与非課税制度」が施行されたのです。簡単に要件と期間について紹介すると・・・
贈与者(教育資金をあげる人)の要件
資金を受け渡すことができるのは、父母・祖父母・曾祖父母といった受贈者の「直系尊属」のみ。第三者や配偶者の親、おじ・おばなどは対象外となる
受贈者(教育資金をもらう人)の要件
受贈者が30歳になっていないこと
- 前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であること
ちなみに、利用期限は令和8年までとなっています。大学生になって一人暮らしをする子供への仕送りなどは、贈与税の対象額に達する可能性が高いため、この制度を上手く利用すべきでしょう。